岡山・倉敷|行政書士が行う相続手続に必要な書類
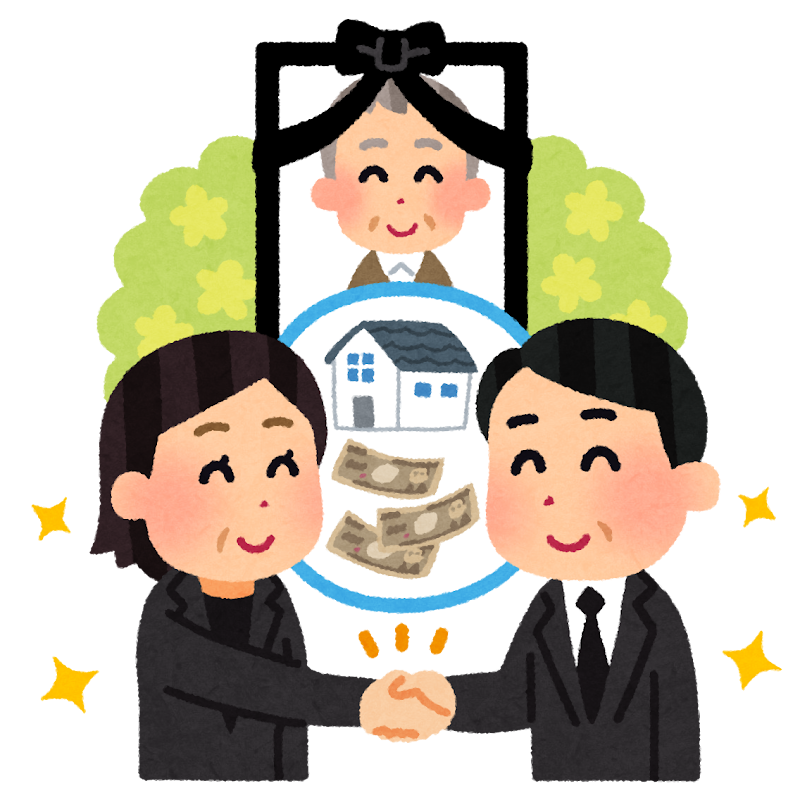
このようなお悩みございませんか?
岡山市にあるスマート行政書士事務所の行政書士 大道一成です。どうぞよろしくお願いいたします。
行政書士が行う相続手続に必要な書類に関して、次のようなお悩み事はございませんか?
遺産分割や相続手続きに関するお悩みごと
- 相続手続きに必要な書類、何が何だかさっぱり分からない…
- 戸籍謄本って、どこまで集めればいいの?種類が多すぎて混乱…
- 不動産の名義変更に必要な書類って、どうやって揃えるの?
- 銀行や証券会社からの書類、これで全部揃っているのか不安…
- 役所と銀行、それぞれで求められる書類が違って手間ばかり…

皆様の、このようなお悩みの解決をお手伝いさせていただきます。
少しでも不明な点があればスマート行政書士事務所にご相談ください。
目次
相続手続きに必要な書類、何が何だかさっぱり分からない…
相続が発生し、いざ手続きを進めようとすると、「あれもこれも書類が必要で、何が何だかさっぱり分からない!」と途方に暮れてしまう方は少なくありません。
ご安心ください。行政書士は、相続手続きの専門家として、皆様のお悩みを解決し、スムーズに手続きを進めるためのサポートをいたします。ここでは、行政書士が相続手続きを行う際に必要となる主な書類について、ケース別にわかりやすく解説していきます。
なぜこんなに書類が必要なの?相続手続きの目的を理解しよう
相続手続きに必要な書類が多いのは、主に以下の目的があるためです。
- 誰が相続人であるかを確定するため: 亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本などから、法定相続人を正確に特定します。
- 相続財産を特定するため: 不動産、預貯金、有価証券など、被相続人の所有していた財産を漏れなく把握します。
- 遺産分割の内容を明確にするため: 相続人全員の合意に基づいて、どのように遺産を分割するかを明確にします。
- 各種名義変更の手続きを行うため: 確定した相続財産の名義を、相続人へ変更するための手続きを行います。
これらの目的を達成するために、様々な公的書類や証明書が必要となるのです。
行政書士が相続手続きで主に収集・作成する書類一覧
行政書士が相続手続きを代行する際に、皆様にご準備いただくか、あるいは行政書士が代理で取得・作成する主な書類は以下の通りです。
1. 被相続人(亡くなった方)に関する書類
これらの書類は、被相続人の出生から死亡までの情報、そして相続人を確定するために非常に重要です。
- 死亡診断書(死体検案書)の写し: 死亡の事実を証明する書類です。死亡届と同時に提出されるため、通常は写しを準備します。
- 戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの): これが相続人特定のための最重要書類です。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得することで、婚姻や転籍の履歴を辿り、すべての相続人を漏れなく把握します。
- 住民票の除票(または戸籍の附票): 被相続人の最後の住所を証明する書類です。不動産の相続登記などで必要となります。
2. 相続人に関する書類
相続人が誰であるか、またその相続人が手続きを行う資格があるかを証明するために必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本: 相続人であることを証明する書類です。被相続人との関係が記載されています。
- 相続人全員の住民票: 住所を証明する書類です。
- 相続人全員の印鑑登録証明書: 遺産分割協議書など、実印を押印する書類に必要となります。発行から3ヶ月以内のものが求められることが多いです。
3. 相続財産に関する書類
被相続人がどのような財産をどれだけ所有していたかを把握するために必要です。
- 不動産に関する書類:
- 固定資産評価証明書: 不動産の評価額を証明する書類です。相続税の申告や、相続登記の登録免許税の計算に必要となります。
- 登記簿謄本(全部事項証明書): 不動産の所在地、面積、所有者などを確認する書類です。
- 公図・地積測量図(もしあれば): 不動産の形状や境界を確認する際に役立ちます。
- 預貯金に関する書類:
- 預貯金通帳・キャッシュカード: 金融機関名、支店名、口座番号などを確認します。
- 残高証明書: 死亡日時点の残高を証明する書類です。金融機関に請求して取得します。
- 有価証券に関する書類:
- 証券会社の取引報告書、残高報告書など: 株式や投資信託などの種類、数量、評価額などを確認します。
- 配当金支払通知書など: 有価証券から得られる収入を確認します。
- 自動車に関する書類:
- 車検証: 車両の登録情報、所有者を確認します。
- 自動車の納税証明書: 納税状況を確認します。
- その他(死亡保険金、退職金など):
- 生命保険証券: 死亡保険金の受取人、金額を確認します。
- 退職金規定、退職金支給通知書: 退職金の有無、金額を確認します。
4. 遺言書がある場合に必要となる書類
遺言書がある場合は、その内容が優先されます。
- 公正証書遺言の場合:
- 公正証書遺言の謄本: 公証役場で保管されている原本の写しです。
- 自筆証書遺言の場合:
- 自筆証書遺言原本: 家庭裁判所での検認手続きが必要です。
- 検認調書(または検認済証明書): 検認手続き後に家庭裁判所から発行されます。
5. 行政書士が作成する主な書類
これらの書類は、上記の収集した情報をもとに、行政書士が作成するものです。
- 相続関係説明図: 誰が相続人であるか、被相続人との関係を図で分かりやすく示したものです。戸籍謄本の内容に基づき作成します。
- 財産目録: 被相続人のすべての財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を一覧にしたものです。
- 遺産分割協議書: 相続人全員で遺産分割の話し合いがまとまった際に作成する書類です。相続人全員が署名・実印を押印します。
- 各種名義変更のための申請書: 不動産の相続登記申請書、預貯金の名義変更届など、個別の財産に応じた申請書を作成します。
「何が何だかさっぱり分からない」を解決する行政書士の役割
これだけの書類が必要となると、やはり「自分一人でできるのだろうか…」と不安に感じるかもしれません。しかし、ご安心ください。行政書士は、これらの書類収集から作成、そして手続き全般にわたるサポートを行います。
具体的には、行政書士は以下のようなサポートを提供します。
- 必要な書類のリストアップと取得代行: 複雑な戸籍の収集や、金融機関からの残高証明書取得などを代行します。
- 相続関係説明図や財産目録の作成: 複雑な情報を整理し、見やすい形で書類を作成します。
- 遺産分割協議書の作成サポート: 相続人の皆様の合意に基づき、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。
- 各種名義変更手続きのサポート: 不動産の相続登記や預貯金の名義変更など、個別の手続きをサポートします。
- その他、相続に関するご相談への対応: 相続手続きに関する疑問や不安に対して、専門的な見地からアドバイスを提供します。
まとめ
相続手続きは、多くの方にとって一生に一度あるかないかの経験です。そのため、「何が何だかさっぱり分からない」と感じるのは当然のことです。しかし、行政書士という専門家が皆様のそばでサポートすることで、これらの複雑な手続きもスムーズに進めることができます。
もし、相続手続きでお困りでしたら、まずは行政書士にご相談ください。皆様の状況に合わせて、必要な書類や手続きの流れを丁寧に説明し、最適な解決策をご提案させていただきます。安心して、一歩を踏み出しましょう。

相続手続きに必要な書類、何が何だかさっぱり分からない…についての要点ポイント
戸籍謄本って、どこまで集めればいいの?種類が多すぎて混乱…
行政書士が教える相続手続きにおける戸籍謄本の全知識
相続手続きを進める上で、必ずと言っていいほど直面する戸籍謄本の壁。「戸籍謄本って、どこまで集めればいいの?」「種類が多すぎて混乱する…」と感じる方は非常に多いです。しかし、戸籍謄本は相続人を確定するための最重要書類。ここを乗り越えれば、手続きは大きく前進します。
行政書士が、この戸籍謄本の「なぜ」「どこまで」「どのように」を徹底解説し、皆様の混乱を解決します。
なぜ戸籍謄本を「出生から死亡まで」集める必要があるのか?
相続手続きにおいて、戸籍謄本を被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡まで」すべて集める必要があるのは、以下の理由からです。
- 法定相続人を正確に確定するため: 戸籍には、婚姻、離婚、養子縁組、認知など、家族関係の重要な情報がすべて記録されています。これらを遡って確認することで、見落としがちな相続人(例:前妻との間に生まれた子、養子など)を漏れなく特定し、相続人間のトラブルを未然に防ぎます。
- 代襲相続人の有無を確認するため: 相続人となるはずだった人が既に亡くなっている場合(例:被相続人の子が先に亡くなっている場合)、その子(被相続人の孫)が相続権を引き継ぐ「代襲相続」が発生します。これを戸籍で確認する必要があります。
- 相続分の確定に必要な情報を得るため: 誰がどれくらいの割合で相続するのか(法定相続分)を確定するためにも、正確な家族関係の把握が不可欠です。
このように、戸籍謄本は単なる死亡の証明書ではなく、被相続人の「人生の家族史」そのものであり、相続の根幹をなす情報が詰まっているのです。
戸籍謄本の「種類」と「集める範囲」を理解しよう
戸籍謄本にはいくつかの種類があり、それぞれ記載されている情報が異なります。相続手続きで主に必要となるのは以下の3種類です。
- 戸籍謄本(現在の戸籍)
- 記載内容: 現在の戸籍に記載されている「戸籍に在籍している全員」の情報が記載されています。氏名、生年月日、父母の氏名と続柄、配偶者の氏名、筆頭者、本籍地、戸籍に入った日などが含まれます。
- 収集範囲: 被相続人の「死亡時点の戸籍」が必要です。
- 除籍謄本
- 記載内容: その戸籍に記載されていた全員が、結婚、死亡、転籍などでその戸籍からいなくなった状態の戸籍です。「全員除籍」された戸籍を指します。
- 収集範囲: 被相続人が過去に転籍したり、結婚などで親の戸籍から出て新しい戸籍を作ったりした場合に、それ以前の戸籍が除籍謄本となります。被相続人の「出生から死亡まで」を辿る過程で、必ずこの除籍謄本が登場します。
- 改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)
- 記載内容: 法改正(戸籍法の改正など)によって、戸籍の様式が変更された際に、古い様式から新しい様式に「改製」される前の戸籍のことです。古い様式で記載されているため、手書きで読みにくいものも多くあります。
- 収集範囲: 現在の様式の戸籍に改製される前の戸籍です。被相続人の出生が昭和中期以前の場合、複数回改製原戸籍謄本を取得する必要があることがほとんどです。
【ポイント】「出生から死亡まで」とは?
現在の戸籍から、一つ前の戸籍、さらにその前の戸籍…と、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を切れ目なく繋げて取得することを意味します。多くの場合、複数の自治体をまたいで取得することになります。
- 例:現在の本籍地 → 転籍前の本籍地 → 結婚前の本籍地(親の戸籍) → 出生時の本籍地
戸籍謄本の具体的な収集手順
戸籍謄本の収集は、以下のステップで進めます。
- 被相続人の「最後の本籍地」を確認する。
- 住民票の除票や死亡時の戸籍謄本に記載されています。
- 最後の本籍地の市区町村役場で「現在の戸籍謄本」を取得する。
- 取得請求書に「相続手続きのため、出生まで遡って戸籍が必要」と明記すると、スムーズに進む場合があります。
- 取得した戸籍謄本の内容を確認する。
- 「従前戸籍(ぜんこせき)」または「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」の欄に、その戸籍の一つ前の戸籍の本籍地が記載されています。
- もし記載がなければ、それが被相続人の出生時の戸籍(またはそれ以前に遡る必要がない戸籍)である可能性があります。
- 一つ前の戸籍の本籍地が異なる場合、その市区町村役場に戸籍謄本を請求する。
- 郵送請求が一般的です。請求書、本人確認書類の写し、手数料(定額小為替)、返信用封筒を同封します。
- 請求書には、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所などを記載し、「〇〇(被相続人名)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)の取得を希望する」旨を明記すると、役所側で判断してくれます。
- 上記3と4を繰り返し、出生まで遡る。
- 途中で本籍地が変わっている場合、その都度、新しい本籍地の市区町村役場に請求します。
- 手書きの古い戸籍は、読解に苦労することもあります。
戸籍謄本収集でよくある質問
- Q: 誰が取得できるの?
- A: 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)、配偶者、またはその代理人(行政書士など)が取得できます。
- Q: 手数料はいくら?
- A: 戸籍謄本・除籍謄本は1通450円、改製原戸籍謄本は1通750円が一般的です。
- Q: 郵送請求の注意点は?
- A: 請求書には、取得する戸籍の範囲(出生から死亡まで)を明確に記載すること。手数料は不足がないように。返信用封筒には切手を貼付し、宛名を正確に記載すること。
- Q: 全部自分でやるのは大変…
- A: まさにその通りです。特に複数の自治体をまたぐ場合や、古い戸籍の読み取りに不慣れな場合は、時間と手間がかかります。行政書士に依頼することで、これらの負担を大幅に軽減できます。
行政書士に戸籍謄本収集を依頼するメリット
「戸籍謄本って、どこまで集めればいいの?種類が多すぎて混乱…」というお悩みを解決するために、行政書士は以下のようなサポートを提供します。
- 正確な戸籍の取得範囲を判断: どの戸籍がどこまで必要か、専門的な知識で判断し、漏れなく取得します。
- 全国の市区町村への請求代行: 遠方の役所への郵送請求手続きを代行し、皆様の手間を省きます。
- 古い戸籍の読解: 手書きで読みにくい改製原戸籍謄本などの内容を正確に読み解きます。
- 効率的な収集: 経験とノウハウに基づいて、最短で必要な戸籍を収集します。
- 相続関係説明図の作成: 取得した戸籍情報をもとに、誰が相続人であるかを一目でわかるように図で作成します。
まとめ
戸籍謄本の収集は、相続手続きの最初にして最大の難関と感じるかもしれません。しかし、「なぜ必要なのか」「どの種類をどこまで集めるのか」を理解すれば、一歩ずつ確実に進めることができます。
もし、ご自身での収集が難しい、時間がない、自信がないといった場合は、行政書士に依頼することをお勧めします。行政書士は、戸籍謄本収集のプロフェッショナルとして、皆様の「戸籍謄本の混乱」を解消し、その後の相続手続きをスムーズに進めるための強力なサポートをいたします。

戸籍謄本って、どこまで集めればいいの?種類が多すぎて混乱…についての要点ポイント
不動産の名義変更に必要な書類って、どうやって揃えるの?
行政書士が導く相続登記の必要書類と揃え方
大切な家族が亡くなり、遺された不動産の名義変更(相続登記)が必要になった時、「一体、何から手をつけて、どんな書類を集めればいいの?」と頭を抱える方は少なくありません。専門用語も多く、どこから情報を得ていいか分からなくなるのも無理はありません。
ご安心ください。行政書士は、相続手続きの専門家として、この不動産の名義変更に必要な書類の準備から、その後の手続きまで、皆様をしっかりとサポートいたします。ここでは、相続登記に必要な書類を「なぜ必要なのか」という理由とともに、具体的な揃え方を解説していきます。
なぜ不動産の名義変更が必要なのか?その重要性
相続によって不動産を取得した場合、速やかに名義変更(相続登記)を行うことが法律で義務付けられています。2024年4月1日からは、相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく申請を怠ると、過料の対象となる可能性があります。
名義変更が必要な主な理由は以下の通りです。
- 所有権の明確化: 誰がその不動産の正当な所有者であるかを公的に示すためです。
- トラブルの防止: 名義変更をせずに放置すると、将来的に売却や担保設定ができない、新たな相続が発生した際に手続きがさらに複雑になるなど、様々なトラブルの原因となります。
- 義務化への対応: 法改正により、相続登記は「義務」となりました。
不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類一覧と揃え方
相続登記には、大きく分けて「亡くなった方の情報」「相続人の情報」「相続財産(不動産)の情報」を証明する書類が必要です。
1. 亡くなった方(被相続人)に関する書類
これらの書類は、被相続人の死亡の事実と、出生から死亡までの家族関係を証明するために必要です。
- 死亡診断書(死体検案書)の写し
- なぜ必要? 死亡の事実を公的に証明するため。
- 揃え方: 死亡届提出時に写しを取っておくのが一般的です。手元にない場合は、病院や役所に問い合わせることも可能ですが、再発行が難しい場合もあります。
- 戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- なぜ必要? 被相続人の出生から死亡までの全ての家族関係(婚姻、離婚、養子縁組など)を証明し、法定相続人を漏れなく確定するため。
- 揃え方:
- 被相続人の最後の本籍地の役所で、死亡時の戸籍謄本を取得します。
- その戸籍に「従前戸籍」や「改製原戸籍」の記載があれば、その本籍地の役所へ遡って請求します。
- これを繰り返し、被相続人が生まれた時点の戸籍まで全て繋げて取得します。
- ポイント: 複数の役所をまたぐことが多く、郵送でのやり取りが基本となります。行政書士が代行することが非常に多い部分です。
- 住民票の除票(または戸籍の附票)
- なぜ必要? 被相続人の最後の住所を証明するため。不動産の登記情報と合致しているか確認します。
- 揃え方: 被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得します。
2. 相続人に関する書類
これらの書類は、誰が相続人であるか、そしてその相続人が名義変更の手続きを行う資格があるかを証明するために必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本
- なぜ必要? 各相続人が被相続人の法定相続人であることを証明するため。
- 揃え方: 各相続人の現在の本籍地の市区町村役場で取得します。
- 相続人全員の住民票
- なぜ必要? 各相続人の現在の住所を証明するため。登記申請書に記載する住所情報として必要です。
- 揃え方: 各相続人の住民票の住所地の市区町村役場で取得します。
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- なぜ必要? 遺産分割協議書など、相続人全員の実印押印が必要な書類に添付し、その印影が本人のものであることを証明するため。
- 揃え方: 各相続人の住民票の住所地の市区町村役場で取得します。発行から3ヶ月以内のものが求められることがほとんどです。
3. 相続財産(不動産)に関する書類
これらの書類は、名義変更を行う不動産の具体的な情報(所在地、面積、評価額など)を証明するために必要です。
- 固定資産評価証明書
- なぜ必要? 不動産の課税評価額を証明するため。相続登記の際の登録免許税の計算根拠となります。
- 揃え方: 不動産の所在地の市区町村役場(または都税事務所など)で取得します。通常、最新年度のものが必要です。
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- なぜ必要? 登記されている不動産の現状(所在地、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者など)を確認するため。
- 揃え方: 全国の法務局で取得可能です。オンライン請求や郵送請求も可能です。
- 公図・地積測量図(任意で提出する場合がある)
- なぜ必要? 不動産の形状や境界を確認する際に参考とします。必須ではありませんが、場合によっては提出を求められることがあります。
- 揃え方: 法務局で取得可能です。
4. 相続関係・遺産分割に関する書類(行政書士が作成をサポート)
これらの書類は、相続人が誰で、どのように遺産を分割したかを明確にするために必要です。
- 相続関係説明図
- なぜ必要? 戸籍謄本を基に、被相続人と相続人の関係を図でわかりやすく示したもの。登記申請の際に添付することで、戸籍謄本の原本還付を受けることができます。
- 揃え方: 行政書士が戸籍謄本の内容を基に作成します。
- 遺産分割協議書
- なぜ必要? 複数の相続人がいる場合、誰がどの不動産を相続するのかを全員で話し合って決定し、その内容をまとめたもの。相続人全員の実印押印が必要です。
- 揃え方: 相続人全員の合意に基づき、行政書士が法的に有効な形式で作成します。遺言書がある場合は不要な場合があります。
- 遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言など)
- なぜ必要? 被相続人が遺言を残していた場合、遺言の内容が遺産分割協議に優先するため。
- 揃え方:
- 公正証書遺言: 公証役場で謄本を取得。
- 自筆証書遺言: 家庭裁判所で検認手続きを受け、検認済証明書付きの遺言書原本を取得(自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要)。
不動産名義変更の書類準備、行政書士に依頼するメリット
「これだけの書類を、自分で全て揃えるのは大変…」と感じるのが正直な感想ではないでしょうか。特に、戸籍謄本の収集や、遺産分割協議書の作成は専門知識が必要で、ミスがあれば手続きが滞る原因にもなります。
行政書士に不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類の収集・作成を依頼するメリットは以下の通りです。
- 必要な書類を正確に把握し、漏れなく収集: 複雑な戸籍の取得代行や、その他の公的書類の取得を代行します。
- 遺産分割協議書などの作成: 法的に有効な形式で書類を作成し、後のトラブルを防ぎます。
- 相続関係説明図の作成: 複雑な相続関係を分かりやすく図示します。
- 司法書士との連携: 不動産登記の専門家である司法書士と連携し、登記申請までスムーズにサポートします。(※行政書士は登記申請の代理はできませんが、必要書類の準備までを一貫してサポートします)
- 時間と手間の削減: 平日に役所へ行く時間がない、遠方の役所への請求が面倒、といった負担を軽減します。
まとめ
不動産の名義変更(相続登記)は、多くの書類が必要となり、その準備には時間と労力がかかります。しかし、相続後のトラブル防止や、義務化への対応のためにも、避けて通ることはできません。
「不動産の名義変更に必要な書類、どうやって揃えるの?」という疑問をお持ちでしたら、ぜひ行政書士にご相談ください。皆様の状況に合わせて、必要な書類の特定から取得、そして作成まで、きめ細やかにサポートし、安心・確実な相続登記のお手伝いをさせていただきます。
不動産という大切な財産を、次の世代へ円滑に引き継ぐために、専門家のサポートをご活用ください。

不動産の名義変更に必要な書類って、どうやって揃えるの?についての要点ポイント
銀行や証券会社からの書類、これで全部揃っているのか不安…
行政書士が導く金融資産の特定と必要書類の揃え方
大切な方を亡くし、相続手続きを進める中で、銀行預金や証券口座の調査は避けて通れない道のりです。しかし、「どの銀行に口座があったのか?」「証券会社はどこを使っていたのか?」「これで本当に全ての金融資産を把握できているのか?」といった疑問や不安に直面する方は少なくありません。
このような時こそ、行政書士が皆様の力になります。この記事では、金融資産の特定から、銀行や証券会社からの必要書類の収集まで、不安を解消するためのポイントをわかりやすく解説します。
なぜ金融機関からの書類収集が不安になりやすいのか?
金融機関からの書類収集が特に不安になりやすいのは、以下の理由が挙げられます。
- 故人の記憶に頼る部分が大きい: 故人が生前、どの金融機関と取引があったか、どのような金融商品を保有していたか、家族が全てを把握しているとは限りません。
- 「隠れた財産」の存在: へそくりや、家族に知られていない口座、投資商品などが存在しないか、という不安がつきまといます。
- 手続きの複雑さ: 各金融機関によって必要書類や手続きが異なるため、個別に対応するのが手間です。
- 残高証明書だけでは不十分な場合がある: 残高証明書は死亡日時点の残高を示すものですが、その口座がいつ開設され、どのような取引があったかまでは分かりません。
まずは「手がかり」を探すことから
不安を解消し、金融資産を漏れなく特定するためには、まず故人の遺品の中から手がかりを探すことが重要です。
- 通帳、キャッシュカード、証券カード: 最も直接的な手がかりです。
- 郵便物、Eメール: 金融機関からの郵送物(定期預金の満期案内、取引報告書、ダイレクトメールなど)や、Eメールの履歴を確認します。
- 確定申告書、源泉徴収票: 利子や配当金の記載から、取引のある金融機関を特定できる場合があります。
- エンディングノート、手帳、メモ: 故人が生前に記録を残している可能性があります。
- 貸金庫の有無: 貸金庫の中に通帳や証券書類が保管されていることがあります。
これらの手がかりを基に、取引のあった可能性のある金融機関をリストアップしてみましょう。
銀行預金の手続きに必要な書類と揃え方
銀行の預貯金口座の相続手続きは、主に以下の流れで進み、それに伴い書類が必要となります。
- 口座の存在確認と残高証明書の取得
- なぜ必要? 故人名義の口座が存在するか、死亡日時点でいくらの残高があったかを確認するため。
- 揃え方:
- 故人が口座を持っていたと思われる銀行に、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を持参し、「残高証明書の発行」と「口座の取引履歴の開示」を請求します。
- 死亡日時点での残高証明書は、相続税申告の有無にかかわらず取得しておくことをお勧めします。
- 取引履歴は、過去の入出金の状況を確認でき、不明な取引の有無や、他の口座の存在を示唆する手がかりになることがあります。
- 請求には、故人の死亡の事実を証明する書類(死亡診断書など)、故人との関係を証明する戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要となります。
- 預貯金の解約・名義変更
- なぜ必要? 故人名義の預貯金を相続人へ引き継ぐため。
- 揃え方:
- 金融機関所定の「相続届」に必要事項を記入し、相続人全員の署名・実印を押印します。
- 添付書類として、一般的に以下のものが必要となります。
- 被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合で、預貯金を特定の相続人が取得する場合)
- 遺言書(公正証書遺言、検認済みの自筆証書遺言など)
- 口座名義人(被相続人)の通帳、キャッシュカード、証書など
- 届出印
- 相続人の本人確認書類(運転免許証など)
- 金融機関によっては、これら以外にも追加書類を求められることがあります。事前に問い合わせて確認しましょう。
証券会社の手続きに必要な書類と揃え方
証券口座の相続手続きは、預貯金口座と似ていますが、株式や投資信託の種類によっては、さらに複雑になることがあります。
- 口座の存在確認と残高証明書(評価証明書)の取得
- なぜ必要? 故人名義の証券口座が存在するか、死亡日時点でどのような金融商品をどれだけ保有していたか、その評価額はいくらかを確認するため。
- 揃え方:
- 取引のあったと思われる証券会社に、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を持参し、「残高証明書(評価証明書)」や「取引報告書(過去の履歴)」の発行を請求します。
- 死亡日時点での評価証明書は、相続税申告に不可欠です。
- 請求には、銀行と同様に、故人の死亡の事実を証明する書類、故人との関係を証明する戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要となります。
- 有価証券の移管・換金
- なぜ必要? 故人名義の有価証券を相続人へ移管するか、換金して分配するため。
- 揃え方:
- 証券会社所定の「相続手続依頼書」などに必要事項を記入し、相続人全員の署名・実印を押印します。
- 添付書類は、銀行手続きと同様のものが基本となりますが、証券会社や保有していた金融商品(上場株式、非上場株式、投資信託など)の種類によって、さらに追加書類(例:被相続人の株主番号、特定口座年間取引報告書など)が求められることがあります。
- 注意点: 上場株式の場合、故人が特別口座ではなく一般口座で取引していた場合や、株券電子化移行前に証券保管振替機構に預けていなかった場合は、手続きが複雑になることがあります。また、非上場株式の場合は、会社独自の相続手続きが必要になる場合もあります。
「これで全部揃っているのか不安…」を解消する行政書士の役割
金融機関からの書類収集は、その数の多さや各機関ごとの違いから、多くの不安を伴います。行政書士は、これらの不安を解消し、スムーズな手続きをサポートします。
- 金融機関の特定サポート: 遺品調査や情報収集から、取引のある可能性のある金融機関を特定するお手伝いをします。
- 必要書類のリストアップと取得代行: 各金融機関の必要書類を正確に把握し、残高証明書や取引履歴などの取得を代行します。
- 戸籍謄本や遺産分割協議書の準備: 金融機関が求める戸籍謄本一式の収集や、法的に有効な遺産分割協議書の作成をサポートします。
- 各金融機関への照会・連絡代行: 複雑な問い合わせや手続きを代行し、皆様の時間と労力を節約します。
- 漏れの確認: 経験に基づいて、金融資産の調査に漏れがないかを確認し、依頼者の「これで全部揃っているのか不安」を解消します。
まとめ
銀行や証券会社からの書類収集は、相続手続きの中でも特に骨の折れる作業の一つです。「これで全部揃っているのか不安…」という気持ちは、多くの方が経験することです。
しかし、適切な手順を踏み、必要な書類を漏れなく揃えることで、故人の大切な金融資産を次の世代へスムーズに引き継ぐことができます。もし、金融機関からの書類収集や手続きでお困りでしたら、行政書士にご相談ください。皆様の状況に応じたきめ細やかなサポートで、不安を解消し、安心して手続きを進められるようお手伝いいたします。

銀行や証券会社からの書類、これで全部揃っているのか不安…についての要点ポイント
役所と銀行、それぞれで求められる書類が違って手間ばかり…
行政書士が教える効率的な相続手続きの書類収集術
相続手続きに直面すると、まずその書類の多さに驚くことでしょう。特に「役所に提出する書類と、銀行に提出する書類が違う」「同じ戸籍謄本でも、銀行では『発行3ヶ月以内』と言われたのに、役所ではそんなこと言われなかった」など、提出先によって異なる要件に戸惑うのは当然です。
この「それぞれで求められる書類が違って手間ばかり…」という悩みを解消し、効率的に書類を収集するためのポイントを行政書士が解説します。
なぜ役所と銀行で求められる書類が違うのか?
役所と銀行(金融機関)では、書類を求める目的が異なるため、それぞれで必要となる書類の種類や要件に違いが生じます。
- 役所(主に法務局、市区町村役場)の目的:
- 戸籍関連: 亡くなった方(被相続人)の法定相続人を公的に確定するため。相続関係図を作成し、相続登記(不動産の名義変更)を進めるための根拠とする。
- 住民票関連: 住所の証明や、固定資産評価証明書の発行など、公的な情報確認や課税のための根拠とする。
- 遺言書関連: 遺言書の検認など、遺言の有効性や内容を確認し、その後の手続きの基礎とする。
- 銀行・証券会社(金融機関)の目的:
- 本人確認・口座名義人確認: 故人の口座が実在し、間違いなく本人であるか、そして相続人が正当な承継者であるかを確認する。
- 資金の保護・適切な分配: 故人の預貯金や有価証券を、法に基づき、かつ間違いなく相続人へ引き渡すため。
- トラブル回避: 後々の相続人同士の紛争や、第三者からの不当な請求を防ぐため、厳格な書類確認を行う。
このように、それぞれの機関が異なる目的を持っているため、必要書類に違いが出てくるのです。
役所と銀行で共通して必要となる「基幹書類」
混乱を避けるためには、まず両者で共通して必要となる「基幹書類」を把握し、優先的に準備することから始めましょう。これらの書類は、一度取得すれば複数の手続きで活用できる可能性が高いです。
【共通の基幹書類】
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 目的: 相続人確定の最重要書類。役所での相続登記、銀行での口座解約・名義変更の両方で必須です。
- 取得方法: 最後の本籍地の役所から遡って、出生までの戸籍を全て取得します。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 目的: 各相続人が法定相続人であることを証明するため。
- 取得方法: 各相続人の現在の本籍地の役所で取得します。
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 目的: 遺産分割協議書など、実印を押印する書類に添付し、その印影が本人のものであることを証明するため。
- 取得方法: 各相続人の住民票のある市区町村役場で取得します。
- 注意点: 発行から3ヶ月以内(または6ヶ月以内)といった有効期限が設けられていることが多いため、必要な手続きの直前に取得するようにしましょう。
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 目的: 複数の相続人がいる場合に、遺産の分割方法を明確にするための合意書。
- 作成方法: 相続人全員の合意に基づいて作成し、全員が実印を押印します。
- 遺言書(遺言がある場合)
- 目的: 故人の意思を尊重し、その内容に基づいて遺産を分割するため。
- 取得・準備方法: 公正証書遺言の場合は公証役場で謄本を取得。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です(自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認不要)。
提出先ごとの「追加で求められる書類」と「注意点」
基幹書類以外に、それぞれの提出先で特に追加で求められることが多い書類や、注意点を確認しましょう。
【役所関連(主に不動産登記の法務局)で追加される書類】
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 目的: 不動産の登記名義人と死亡時の住所を紐付けるため。
- 取得方法: 最後の住所地の市区町村役場で取得。
- 固定資産評価証明書
- 目的: 不動産の評価額を証明し、相続登記の登録免許税を算出するため。
- 取得方法: 不動産の所在地の市区町村役場(または都税事務所など)で取得。最新年度のものが必須。
- 相続関係説明図
- 目的: 戸籍謄本の内容を分かりやすく図示したもの。登記申請の際に添付することで、戸籍謄本の原本還付が受けられる。
- 作成方法: 行政書士が戸籍謄本を基に作成。
【銀行・証券会社(金融機関)で追加される書類】
- 被相続人の預貯金通帳、キャッシュカード、証書など
- 目的: 口座の特定と確認。
- 残高証明書(死亡日時点のもの)
- 目的: 死亡日時点の残高を確認するため。相続税申告にも必要。
- 取得方法: 各金融機関に直接請求。
- 取引履歴(過去数年分)
- 目的: 不審な出金がないか、他の金融機関との取引の形跡がないかなどを確認するため。
- 取得方法: 各金融機関に直接請求。
- 各金融機関所定の「相続届」
- 目的: 金融機関が定めた相続手続きの申請書。
- 取得方法: 各金融機関の窓口やウェブサイトで入手。
効率的な書類収集のための「行政書士活用術」
「役所と銀行、それぞれで求められる書類が違って手間ばかり…」という悩みを根本的に解決するのが、行政書士のサポートです。
- 包括的なリストアップ: 必要な手続き全体を把握し、役所、銀行、その他どこに何が必要かを一度にリストアップします。
- 戸籍謄本の一括取得: 最も手間がかかる被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)を、複数の役所をまたいで全て取得代行します。これにより、各機関に提出する際の戸籍の準備が一度で完了します。
- 共通書類の複数取得・コピー対応: 提出先に合わせて、共通書類(印鑑証明書など)を必要な部数取得したり、原本の還付請求とコピー提出を使い分けたりするなど、効率的な運用を提案・実行します。
- 各金融機関への照会・対応代行: 金融機関ごとに異なる手続きや求められる書類を正確に把握し、問い合わせや手続きを代行します。
- 遺産分割協議書、相続関係説明図の作成: 複雑なこれらの書類を、法的に有効かつ分かりやすい形で作成します。
- 司法書士や税理士との連携: 必要に応じて不動産登記や相続税申告の専門家と連携し、手続き全体をスムーズに進めます。
まとめ
役所と銀行で求められる書類の違いは、その目的が異なるために生じるものです。この違いを理解し、まずは共通で必要となる基幹書類を効率的に収集することが、手間を減らす第一歩となります。
しかし、やはり個人で全てを把握し、漏れなく揃えるのは容易ではありません。「役所と銀行、それぞれで求められる書類が違って手間ばかり…」と感じたら、ぜひ行政書士にご相談ください。行政書士は、皆様の書類収集の負担を軽減し、複雑な相続手続き全体を、安心かつスムーズに進めるための強力なパートナーとなります。
もう書類の山に埋もれて途方に暮れる必要はありません。専門家のサポートを活用して、効率的に手続きを完了させましょう。

役所と銀行、それぞれで求められる書類が違って手間ばかり…についての要点ポイント
まとめ

相続手続きについてご不安な方へ
大切な家族との円満な遺産分割や相続手続きについて、少しでも不明な点があればスマート行政書士事務所にご相談ください。
対応地域
対応地域(はじめての方でもお気軽にご相談ください)
岡山県全域の市区町村(岡山市・倉敷市)
岡山市 北区、岡山市 南区、岡山市 中区、岡山市 東区
倉敷市、津山市、総社市、玉野市、笠岡市、赤磐市、真庭市、井原市
瀬戸内市、浅口市、備前市、高梁市、新見市、美作市
和気町、矢掛町、早島町、美咲町、鏡野町、里庄町、勝央町、吉備中央町、奈義町、久米南町
西粟倉村、新庄村

